記事公開日
最終更新日
来年は未年 新聞記事から
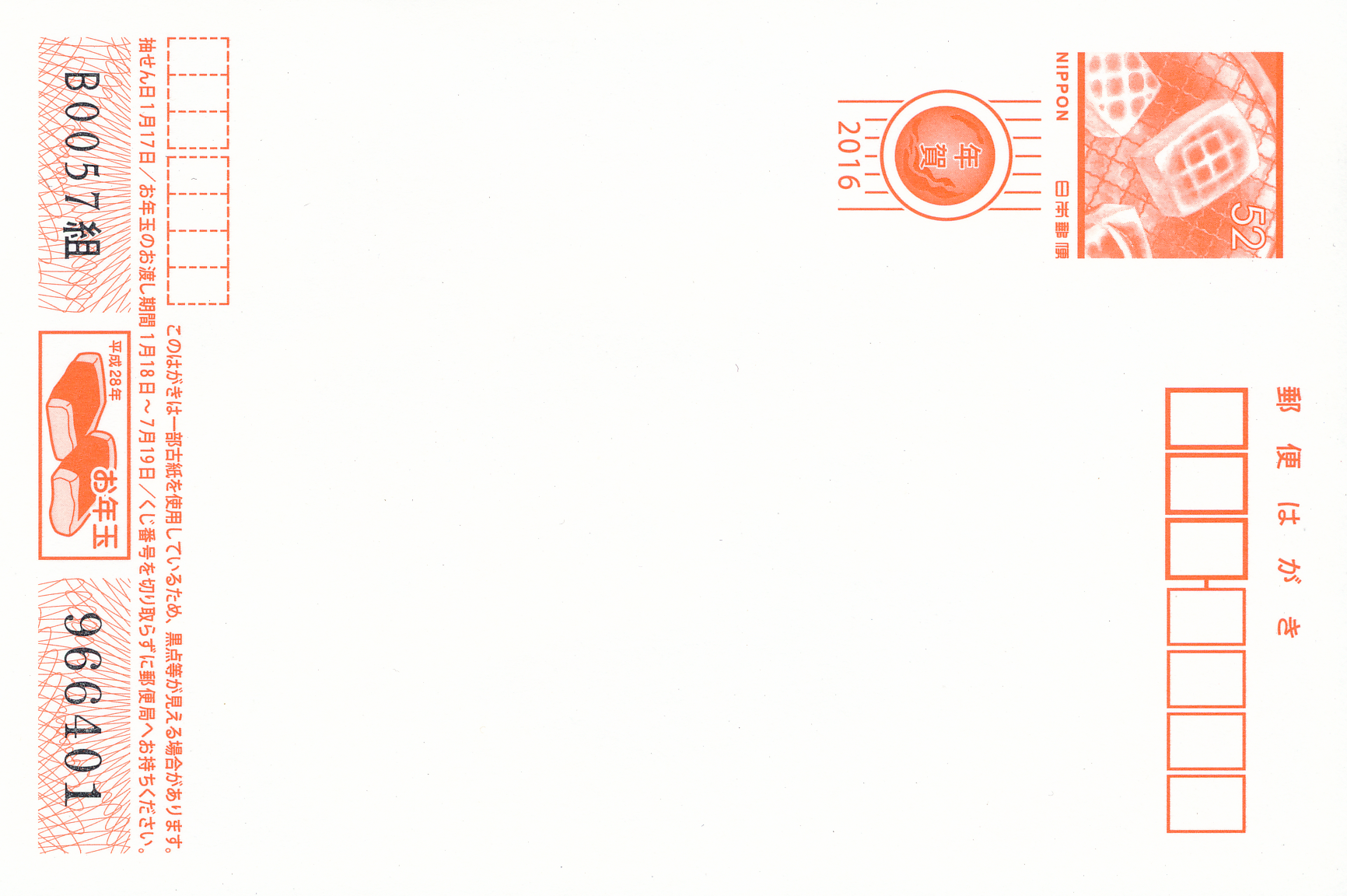
去年の11月5日の毎日新聞 の記事から
一年前の、ちょっと古い新聞記事ですが、面白かったので切り抜いていました。
何かの参考になればと、紹介します。
来年は未年 羊と書かない?
「年賀状の発売が既に始まっている。1月元旦の朝に届けられるよう、又早くから準備したいものだ。
来年は羊年。えとの羊について調べてみょう」
と原稿に書きかけた新人記者の新くん。すかさず「ちょつと待った!」と校閲記者 新くんへのダメ出しが入ります。「今の文章 直すところだらけですよ」。
はて、どこが不適切だったのでしょう。読者の皆さんも、説明される前にどう直すのが適切か、考えてみてください。
新 読み直しましたが、誤字も脱字もないと思いました。どこが問題なのですか?
閲 まず冒頭の「年賀状」ですが、「年賀はがき」とすべきです。
新 年賀状と年賀はがきって違うものなのですか?
閲 ふつう、売り出すときは「年賀はがき発売」、書いて出すときは「年賀状を書く」「年賀状を出す」などと使い分けます。
新 そうか、書く前のものが「はがき」なんですね。
閲 郵便局でも「年賀はがき販売中」などの張り紙があるはずですよ。
新 なるほどー。で、他の間違いは?
閲 「発売」って、売り始めることですよね。
新 もちろん・・・・・・あ、そうか、「販売が始まっている」だと「始まる」の意味がダプってしまう?
閲 その通り。「年賀はがきの販売が既に始まっている」か年賀はがきが既に売り出されている」にすべきです。
新 なるほどー。もう大丈夫ですね。
閲 いやいや。「1月元旦の朝」もなんとかしなきゃ。
新 ああ。そういや「1月」は余計でしたね。元日ほ1月に決まっていますから。
閲 それだけじゃありません。「の朝」も余計です。元旦といえば 1月1日の朝のことですから。
新 元旦だけでよかったのか。
閲 ちなみに「旦」の字は日の出を意味します。水平線から太陽が出ることを表す字なのです。
新 なるほどー。もう大丈夫ですよね。
閲 いやいや「羊年」が違うでしょ。
新 ははあ、「未年」とも書くのは知っていますけど、「羊年」の方が読みやすいでしょ?
「未年」だと「みどし」と読まれそうです。
閲 確かに、常用漢字表の「未」に「ひつじ」の読みはありません。しかし本来、十二支と動物とは関係ないのです。
十二支は昔、方角や時間などにも使われましたが、「羊の刻」「牛虎の方角」などとは書きませんよね。
新 そういえば、土用の「うしの日」は「丑の日」と書きますね。
閲 ですから年のことを漢字で書くときば「未年」がよいでしょう。
新 未の字はそもそもどういう成り立ちがあるのですか。
閲 未は象形文字で、枝が茂っている木の形(平凡社「常用字解」)とも、木のまだ伸びきらない部分(学研「漢字源」)ともされます。いずれにせよ動物ではなく植物と関係が深いのです。
新 じゃあ今年の午ってなぜ牛みたいな字なんですか。
閲 穀物をつく杵のもとの字と考えられます。
馬とも牛とも関係ありません。動物に当てたのは「漢字源」によると、覚えやすいようにという古代中国の暦の影響ということです。
新 でも動物羊が年末年始に頻出することは事実ですよね。羊の絵とか置物とか。その記事で「えとの羊」って書いたらいけないのですか?
閲 校閲では「えとの羊」という言葉は「えとにちなんだ羊」と直しています。
新 そうだったんですか。ではさっきの文を直します。えーと「年賀はがきが既に売り出されている。元日に届けられるよう、早くから準備したいものだ。
来年は未年。えとにちなみ羊について調へてみよう」 。これでどうです?
閲 いいですね。でも、なんだか動物の羊の話がしにくくなりました。
まさに「亡羊の嘆」
新 何ですって?
閲 枝道が多いため逃げた羊を見失うということから、どうしてよいか分からないことを表す言葉です。
以上、新人君がの原稿を先輩がダメ出し・・・と言った内容でした。を元に、解説しているものでしたが、ちょっとまとめてみました。
「年賀状の発売が既に始まっている。1月元旦の朝に届けられるよう、又早くから準備したいものだ。
来年は羊年。えとの羊について調べてみょう」
何も問題無いように見える記事ですが
1、冒頭の「年賀状」ですが、「年賀はがき」とすべきです。
ふつう、売り出すときは「年賀はがき発売」、書いて出すときは「年賀状を書く」「年賀状を出す」などと使い分けます。
書く前のものが「はがき」なんですね。
郵便局でも「年賀はがき販売中」などの張り紙があるはずですよ。
2、「発売」って、売り始めることですよね。
「販売が始まっている」だと「始まる」の意味がダプってしまう?
「年賀はがきの販売が既に始まっている」か年賀はがきが既に売り出されている」にすべきです。
3、「1月元旦の朝」もなんとかしなきゃ。
ああ。そういや「1月」は余計でしたね。元日ほ1月に決まっていますから。
「の朝」も余計です。元旦といえば 1月1日の朝のことですから。
ちなみに「旦」の字は日の出を意味します。水平線から太陽が出ることを表す字なのです。
4、「羊年」が違うでしょ。
常用漢字表の「未」に「ひつじ」の読みはありません。しかし本来、十二支と動物とは関係ないのです。
十二支は昔、方角や時間などにも使われましたが、「羊の刻」「牛虎の方角」などとは書きませんよね。
土用の「うしの日」は「丑の日」と書きますね。
ですから年のことを漢字で書くときば「未年」がよいでしょう。
未は象形文字で、枝が茂っている木の形(平凡社「常用字解」)とも、木のまだ伸びきらない部分(学研「漢字源」)ともされます。いずれにせよ動物ではなく植物と関係が深いのです。
今年の午ってなぜ牛みたいな字なんですか。
穀物をつく杵のもとの字と考えられます。
馬とも牛とも関係ありません。動物に当てたのは「漢字源」によると、覚えやすいようにという古代中国の暦の影響ということです。
年末年始に頻出する羊の絵とか置物とか。その記事で 校閲では「えとの羊」という言葉は「えとにちなんだ羊」と直しています。
以上のダメ出しの結果
「年賀はがきが既に売り出されている。元日に届けられるよう、早くから準備したいものだ。来年は未年。えとにちなみ羊について調へてみよう」
元の記事
「年賀状の発売が既に始まっている。1月元旦の朝に届けられるよう、又早くから準備したいものだ。来年は羊年。えとの羊について調べてみょう」
わたくし、小学校に戻って、国語の勉強をやり直しする必要があるような気がします。




